著者は不安という言葉は第二次世界大戦後に生まれ定着し、その前までは宗教と哲学で定義された道徳的立場が人間の選択の拠り所だったと述べています。
つまり選択に悩み決断することを強いられる過程から不安が生まれますので、選択の自由の増大が不安の増大に繋がります。
信仰の時代から人間は自分達の境遇をより良くすることに努めてきましたが、そもそもそのより良くする事に努めることが不安の始まりにもなります。
そして『人間には選択の自由がある』という実存主義の発達によって、人間の自由が増大するにつれ不安はより増大することに繋がりました。
自由民主主義の発展によって、選択の自由はより進み決断への戸惑いを招き不安を呼び込みますが、実は自由が人間の心を不自由にして不安からの鬱病の増大に繋った悪循環です。
キルケゴールは不安が人間の行動を支配する原動力の一部と言っていましたが、サルトルのように人間は何をすべきなのか? 自分の運命さえも知る術を持たない元々が孤独な存在であって、人生に問題とされるものではないと結論づけた方が実は楽に生きられるように思えます。
脳神経学的には不安からの病気には脳内に原因がある内因性のものと、環境が原因の外因性のものがあると述べています。
内因性の鬱病は遺伝的要因があり、本人が望まない環境に投げ込まれた時に発症し、統計的調査では脳の構造的欠陥が予測されるそうです。
外因的要素は努力行動に対して報酬が報われないことに起因する要素が多くを占めていて、不安の先の様々な恐怖症に進む前に適切な心理療法的な治療を施すとほとんどが治癒できると言ってます。
外因的要素では、さほど努力しないで報酬を期待する人ほど鬱病にかかりやすいことになりますが、現代社会の誰の人生において大切なことは全ての選択の結果は『選んだ自分自身にも半分責任がある』という認識を背負って生きると鬱病になりにくいと思います。
何故なら受け入れたくない事実との葛藤が苦悩を生むのであるので、受け入れると覚悟が決ってしまい、果たしてどう対処すべきか? と前向きに捉えられるようになるからです
今までの不安が人間のネガティブな感情とすると、ポジティブな感情は愛ではないか? と思いますが、著者は愛は最も複雑な感情と述べています。
人間が生まれ、親への愛着(生物学的必然性)から成長するにつれて恋愛から友愛へと移行(文化的影響)する人間の最も優しい感情で、これは文化的影響が愛情の形態に対する解釈に大きく影響を与えるそうです。
犬の赤ん坊の時に三グループに分けて育てた研究が印象的で、第一は愛情だけを注ぐ・第二は敵視する・第三は愛情と敵視が交錯した中で育てた結果、第三グループが訓練士に一番良くなついたそうです。
つまり時に可愛がられ、時に叱られる環境が好ましく、愛情と敵視の微妙なバランスが脳の高揚と満足を生み出し、幼児期にこのような経験が多いほどしつけの問題が減少することに繋がっているとの結果です。
人間の赤ちゃんは泣いた時は興奮状態に、そして親にあやされて鎮静状態を繰り返すのですが、その経験が脳にフィードバックされて愛着から成長過程で愛情と解釈され認識する事に繋がって行くそうです。
そして人によって同じ出来事に感情の高揚に違いが起こるのは、その出来事への脳内のイメージの解釈の違いによって『愛』という興奮が起こるか? 否か? が決定されるのですが、これは遺伝も含めた複合的作用によると述べています。
恋をして胸が高鳴り頬が紅潮するのは生物学的要因で誰にでも起こりますが、愛情の解釈に影響を与えるのが文化的影響と捉えると、ストーカーや虐待やDV等の変質した愛の感情は甘やかされ過ぎか? 厳しく虐待されたか? などの要因があり、愛情と敵視の微妙なバランスで育てられなかった結果ではないか? と思ってしまいます。
飴だけでも鞭だけでも駄目で、硬軟入り混ぜた微妙なバランスで育てることがバランスの取れた人間を作るのでしょう。
大人社会においても人を動かす人事の要諦は飴と鞭、人間社会の縮図は全てバランスに集約されているのかな? と思うと共に、私の気に入っている坂本龍馬の『厚情だけが情けにあらず、薄情もまたこれ情けなり』の信念の言葉を想い出しました。
 幸せであることを
意識できる生活
幸せであることを
意識できる生活
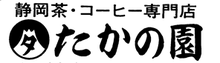
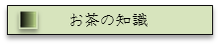




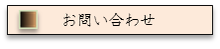

コメントをお書きください